
飲食店の倒産が増えているようです。
毎年、12月に出る帝国データバンクの「外食産業の倒産動向調査」によると、2011年の負債1,000万円以上の飲食業倒産件数は、648件(1-11月)で過去最高だと言う事です。
昨年は、震災や原発事故やO-111食中毒もあり、苦しさを増す飲食業にとって、更に追い打ちをかける社会環境となりました。
今年は、やや持ち直しているようにも見えますが、小麦や油の原材料価格も上昇していますし、電気代の値上げも行われます。
更に厳しい環境が続きます。
私が定点観測をしている、吉祥寺でも日々閉店と新規開店の繰り返しが、行われています。
しかし、私のような、飲食マニアから見れば、そんな閉店も、もう一掘り、深掘りすれば、出血をしなくて済んだり、しても少なくて済んだりするのになあ~と言う風に見えるのです。
あまりにも、残念な出店が多いのです。
「良い出店」があまりにも少ないのです。
「良い出店」をすれば、当然のことながら、閉店リスクは低下します。
つまり、閉店は、「良い出店」でないケースがほとんどなのです。
「良い出店」とは、良い商品を、良い場所に、適正な価格で、効果的な告知をし、良い人材で販売する環境を整える事、です。
繰り返しますが、これをちゃんと出来ている店が非常に少ない。
「商品」に溺れ、「場所」に溺れ、その強みを生かせていない。
「どこにでもある商品」を「不思議な場所」で、「誰にも知らせず」、「ありきたりの接客」で売ろうと目論んでいる店も、驚くほど多い。
大きな投資をして、勝負を掛けているはずなのに・・・・
そして、あげくは「こんなはずじゃあなかった、のに・・・」と肩を落とす経営者・・・
では、「どんなはずだったのでしょうか?」
多くの閉店店舗、倒産企業は、この「こんなはず」と言う目論見が、「理論値」ではなく「期待値」いや「希望値」になっているのです。
「理論値」ならば、目論見通りではなかったときに、その原因の差を分析出来ます。
だから、リカバリー策が取りやすいのです。
これが、「期待値」「希望値」の場合、原因の差を測る事が出来ないのです。
だから、対策の一手も、空振りの確率が高くなる。
店舗ビジネスは、「どこの」「誰に」「何を」「いくらで」「どんな告知をして」「誰が」売るかで、大きな差が出ます。
それを、ひとつひとつ、調査して仮説を立てて(これが理論値)、それを、戦略にして、計画を立てる事を事前にするから,計画と実績の違いが具体的に見えてくるのです。
ほんの数日の簡単な調査で出来る、この事前調査を面倒くさがるので、大きな損失につながるのです。
新店開発で業績を伸ばそうと思っている経営者の皆さん!
後で後悔する前に、開店前に「ほんの少しの手間」を掛けてみませんか?
※ご相談はこちら→ info@peopleandplace.jp



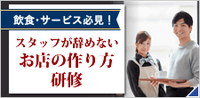


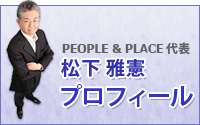
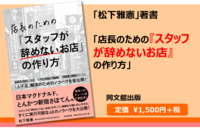

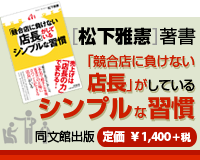







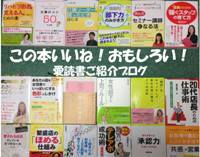


この記事へのコメント
それを、ひとつひとつ、調査して仮説を立てて(これが理論値)、それを、戦略にして、計画を立てる事を事前にするから,計画と実績の違いが具体的に見えてくるのです。
この記事へコメントする